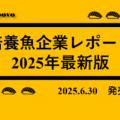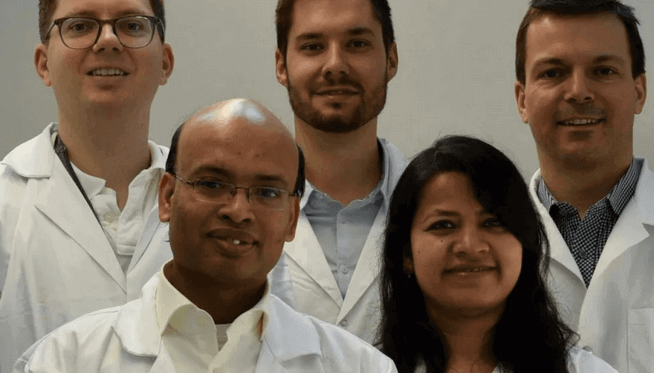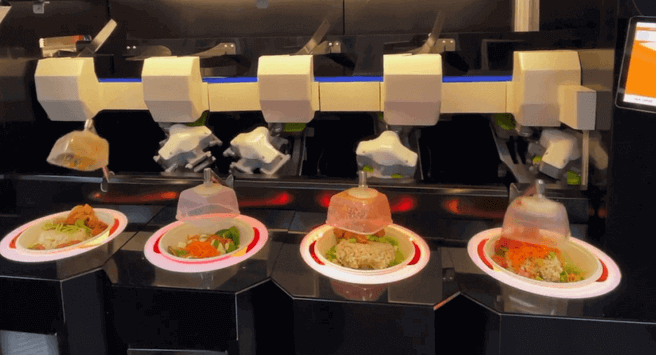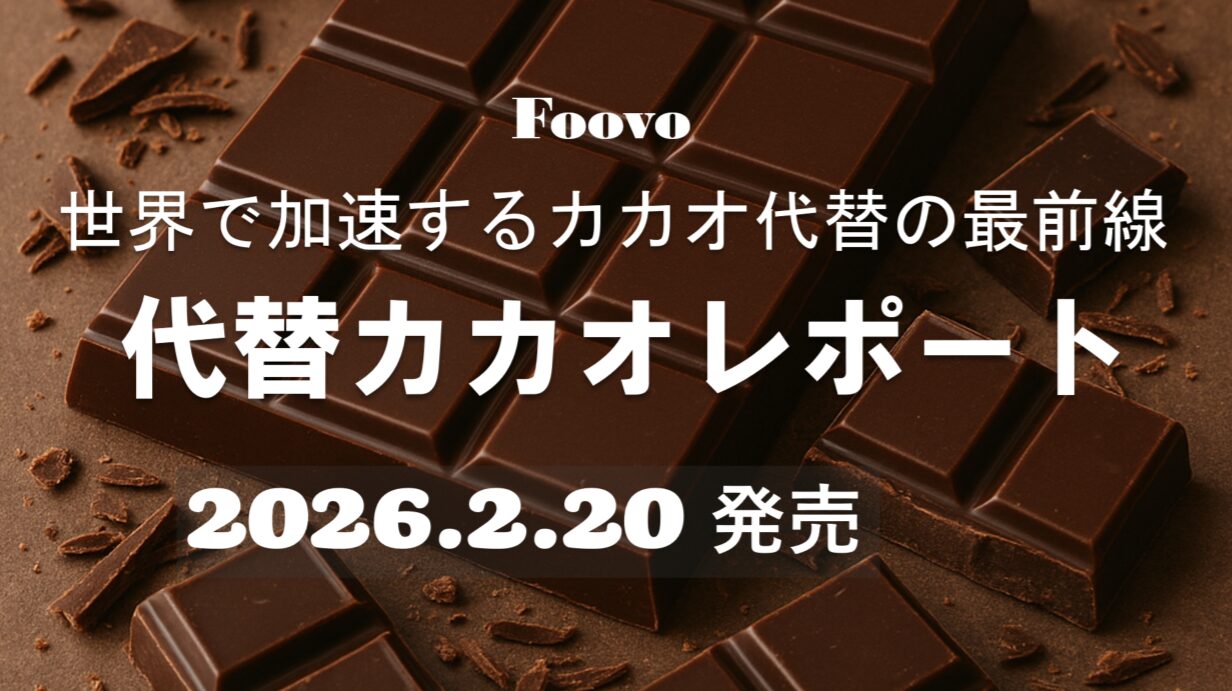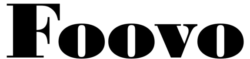写真:Gourmey
フードテック官民協議会の細胞農業ワーキングチームは2025年8月18日、培養細胞を原料とする食品カテゴリの名称について、「細胞性食品」を基本的名称とする方針を発表した。
これまで「培養」、「細胞培養」、「細胞性」などさまざまな呼び方が混在していたが、関係者間で可能な限り単一の名称を用いることで、業界全体の信頼性を高め、メディアや消費者の混乱を軽減することが狙い。
名称方針の策定にあたっては、食品メーカーの研究者や、食品製造、流通・小売、食品安全、消費者団体の関係者など、外部有識者からも広く意見を集めた。
細胞性食品には肉だけでなく、魚やミルクなども含まれる。今回の名称方針に照らした具体例としては、「培養鶏肉」は「細胞性鶏肉」、「培養牛肉」は「細胞性牛肉」、「培養シーフード」は「細胞性シーフード」、「培養ミルク」は「細胞性ミルク」といった呼び方が想定される。
名称方針の策定では、科学者にとっての分かりやすさだけでなく、消費者とのコミュニケーションの円滑化、食産業全体のステークホルダーが納得できるか、国際的な用語との整合性などを検討した。また、養殖魚や発酵食品など、従来の食品と混同されないことも重視した。
実際に、NEDOの助成を受けて6,000名(20代-60代)を対象に2024年に実施された調査では、「細胞培養」や「培養」という名称では、養殖魚など従来の食品と混同される傾向が、「細胞性」と比較して約19~25%高いことが明らかになった。
「培養」や「細胞培養」という用語は科学者には理解しやすいが、消費者に正確な理解を促すとは限らない。そのため、消費者に「新しい食品」であること、従来の食品とは異なることを名称から直観的に伝えるために、「細胞性」が望ましいとされた。
ただし、「細胞性」という名称には、“細胞でできているあらゆる食品が含まれている”ように見える恐れや、初見では意味が伝わりにくいなど、一定の弱点や誤解のリスクも存在するため、名称使用とともに「丁寧な説明と補足の工夫が不可欠」だと提言されている。
また、研究者間の専門的な会議など誤解の余地が少ない場面では、技術ベースの名称を使用する妥当性はあるという。
細胞農業ワーキングチームは今後、「細胞性食品」の理解促進に向けた説明や資料の開発を進める予定だ。国内では細胞性食品はまだ上市されていないが、上市の目途が立ち次第、ラベル・表示に関する自主ルールの検討や、認証マークや規格化などの検討を進めていくとしている。
※本記事は、プレスリリースをもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。
関連記事
アイキャッチ画像の出典:Gourmey