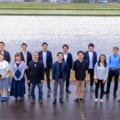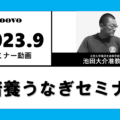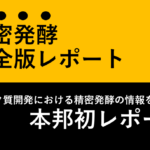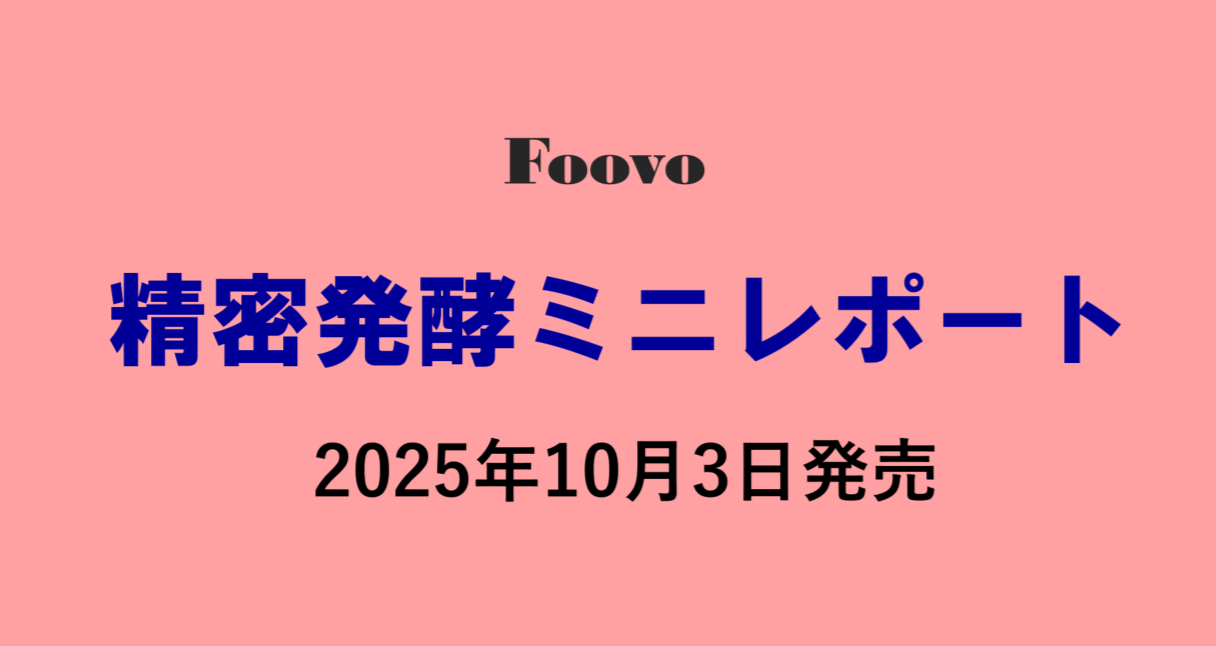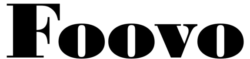出典:高木博史特任教授
2025年9月9日更新
奈良県に、発酵(伝統・バイオマス・精密発酵)をキーテクノロジーに酵母の機能を活用したスタートアップ立ち上げに挑もうとする人物がいる。
奈良先端科学技術大学院大学の高木博史特任教授だ。
味の素から福井県立大、奈良先端大に至るまで、長年、応用微生物学研究に従事し(2022年春の紫綬褒章を受章)、多くの国際学会で研究成果を発表してきた高木特任教授には、解せない思いがあった。
日本が培ってきた微生物の分離・育種研究や発酵・醸造技術は世界で大きな強みになる。しかしながら、この分野で存在感を示す日本のプレーヤーが海外にほとんど見当たらない。アメリカでは日本酒の関連会社が増えており、日本の発酵・醸造技術をリスペクトする雰囲気が社会で醸成されつつある。
それならばなおさら、日本人がアピールすべきではないのか―。
高木特任教授は産業界からアカデミアまでの豊富なキャリアパスと自身が構築した様々なネットワークを活かし、シニア起業に挑む決意を固めた。定年退職から2年半が過ぎた現在、海外のフードテックが注目する発酵(伝統・バイオマス・精密発酵)をベースとするスタートアップ立ち上げを計画している。
「日本は微生物の分離・育種と発酵・醸造技術に世界的な強みがあります。伝統発酵で培った突然変異育種の技術をバイオマス発酵や精密発酵へと拡張し、この分野における日本の存在感を世界に示したいのです」(高木特任教授)
GMO・非GMOの二刀流戦略

高木博史特任教授(高木特任教授提供)
今年6月、農研機構の生研支援センター(BRAIN)の「スタートアップ総合支援プログラム(SBIR支援)」に、高木特任教授のプロジェクトがフェーズ1で採択された。
採択された中で唯一のバイオマス・精密発酵プロジェクトだった。期間は1年間で、助成金額は最大1,000万円。
テーマは、トルラ酵母を用いたバイオマス発酵による代替タンパク質の開発、そして精密発酵に必要な酵母の新しいゲノム編集技術の確立だ。
本記事はFoovoによるインタビュー記事です。
インタビュー実施日:2025年8月21日
関連記事
アイキャッチ画像の出典:高木博史特任教授