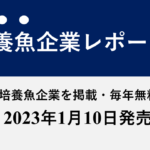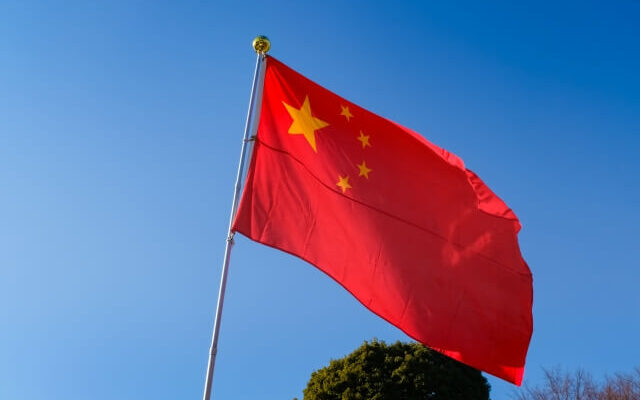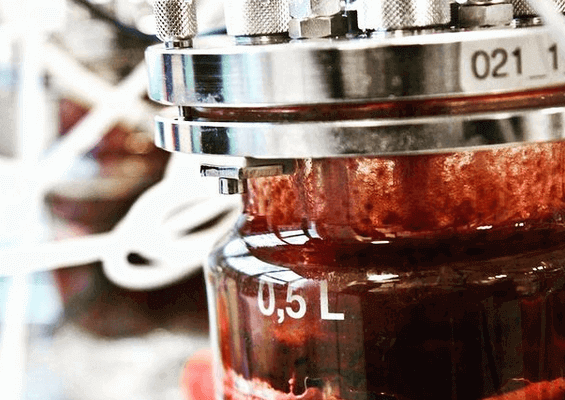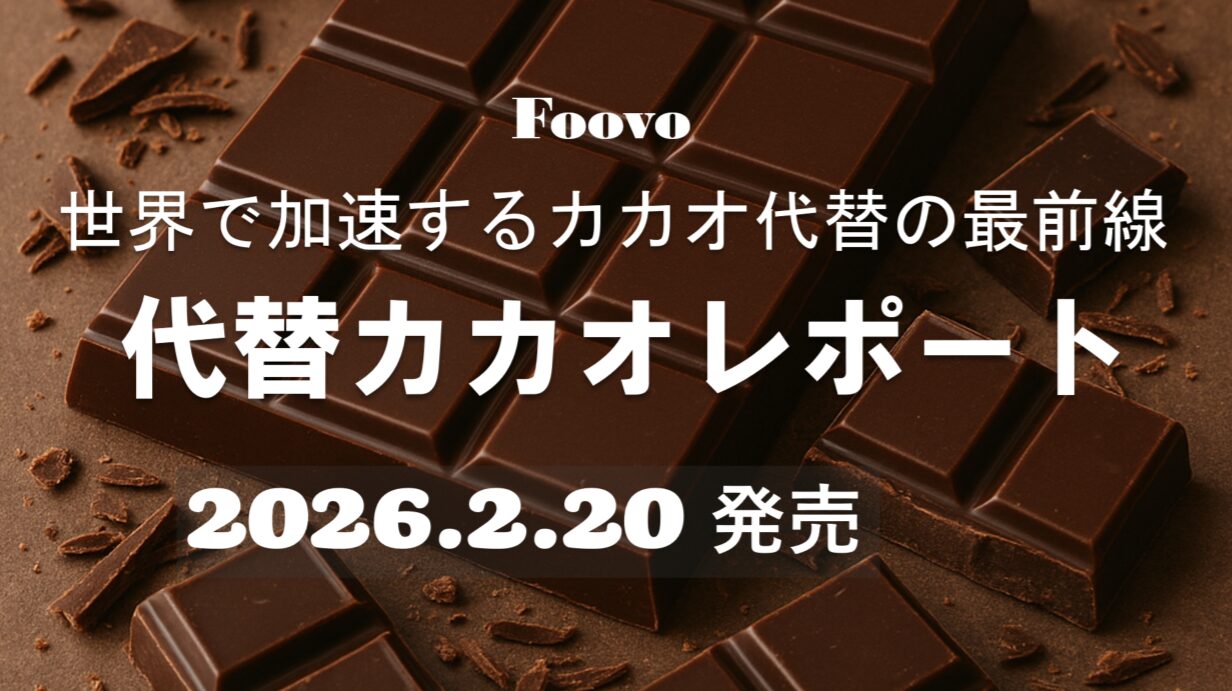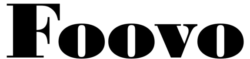2025年7月18日追記
3Dプリンターで代替肉・魚を開発するイスラエルのSteakholder Foodsは7月14日、同社のプレミックスを使用した植物性の「白身魚ケバブ」と「サーモンパティ」が、イスラエル全土のヴィーガン専門店で発売されたと発表した。
製造は、ホテルやレストランなどB2B向けにヴィーガン/ベジタリアン製品を製造販売するパートナー企業Bondor Foodsが担当し、パイロット生産を経て商業規模の生産に移行している。
今回の製品発売は、2024年9月30日に発表された初回注文に基づくものであり、Steakholder Foodsにとっては「プレミックス供給から消費者販売に至るまで、初めて製品サイクル全体での収益化」が実現した形となる。
同社の「プレミックス」は、植物原料から開発された3Dプリンター用の「バイオインク」を指す。
植物ステーキ用のプレミックス(水、大豆、小麦など)、白身魚用のプレミックス(水、大豆、酵母、菜種油など)などが開発されており、ステーキや白身魚といった構造体の生成には、それぞれ同社のMX200プリンター、HD144プリンターが前提とされている。同社のプレミックスは通常、3Dプリンターで最終形状を得る設計だが、今回の製品について3Dプリンター使用の有無はプレスリリースでは言及されていない。

MX200プリンターで作られた植物性ステーキ 出典:Steakholder Foods Instagram
今回の製品はGreen Futureブランドでの販売であり、Steakholder Foods自身が消費者向け製品を手がけるわけではない。実際、同社は年次報告書(p.13)において「消費者向け製品の製造・流通・販売は行わず、プリンター事業の商業化に専念する」と明言しており、事業モデルはB2Bに特化している。
今回の製品発売により、プレミックス供給→製造→消費者販売という一連の流れで初めて売上が立ったこととなり、Steakholder Foodsにとって大きな前進といえる。
3Dプリンターを用いた代替魚では、オーストリアのRevo Foodsも知られる。同社はサーモン、タコ、白身魚などの代替シーフードを展開し、昨年にはウィーンで3Dプリンティング工場を開設した。一方、Steakholder Foodsは、プリンターやバイオインクのB2B販売に注力しており、両社の事業モデルは対照的といえる。
培養肉を見据えた段階的展開

サーモンパテ 出典:Steakholder Foods Instagram
Steakholder Foodsの培養肉事業の行方が気になるFoovo読者も多いだろう。
同社が現在焦点を当てる植物性食品事業は、もともと培養肉開発から出発した同社の新たな戦略である。Steakholder Foodsは2019年の設立当初から培養肉の開発に取り組んできたが、今年3月に発表された年次報告書(p26 Business Overview)によると、2023年に植物性食品向け3Dプリンターとプレミックスの商業化へと、戦略的な事業転換を図った。
培養肉は規制承認プロセスが長期化するため、まず植物性の肉・魚の3Dプリンター事業で収益化を優先する方針に移行した。現在は植物性製品で実績を積み上げながら、将来的には培養肉と植物性素材を組み合わせた「ハイブリッド肉」の開発を目指している。
2024年9月には、同社初の本格的なデモンストレーションセンターを開設し、MX200プリンターとHD144プリンターの実演を通じて導入企業の拡大を狙っている(年次報告書・p26 Business Overview)。
この段階的アプローチにより、規制リスクを回避しながら技術基盤と市場でのポジションを確立し、最終的には培養肉の市場投入を狙っていることがうかがえる。
同社は昨年10月、Wyler Farmから植物ステーキ用のプレミックスの初注文を受けた。製品は同社施設で製造され、Wyler Farmブランドで2025年の販売が予定されている。また、UMAMI Bioworksとの2年間にわたる協業も昨年11月に終了し、3Dプリンターによる培養魚製品の量産化に一定の目途が付いたと報告されている。
今回の植物魚製品の小売導入に続き、植物ステーキ製品の市場投入も近いとみられる。並行して進む培養肉の開発動向も注目される。
※本記事は、プレスリリースをもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。
関連記事
アイキャッチ画像の出典:Steakholder Foods