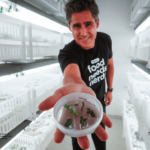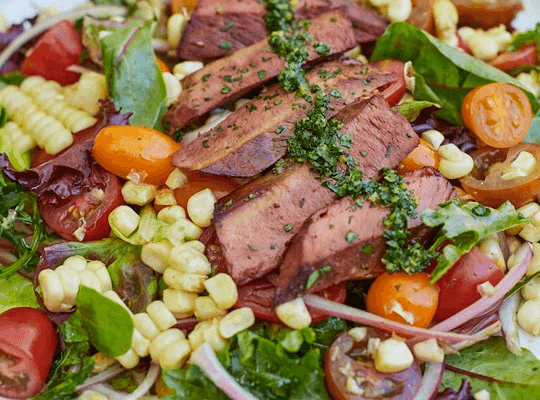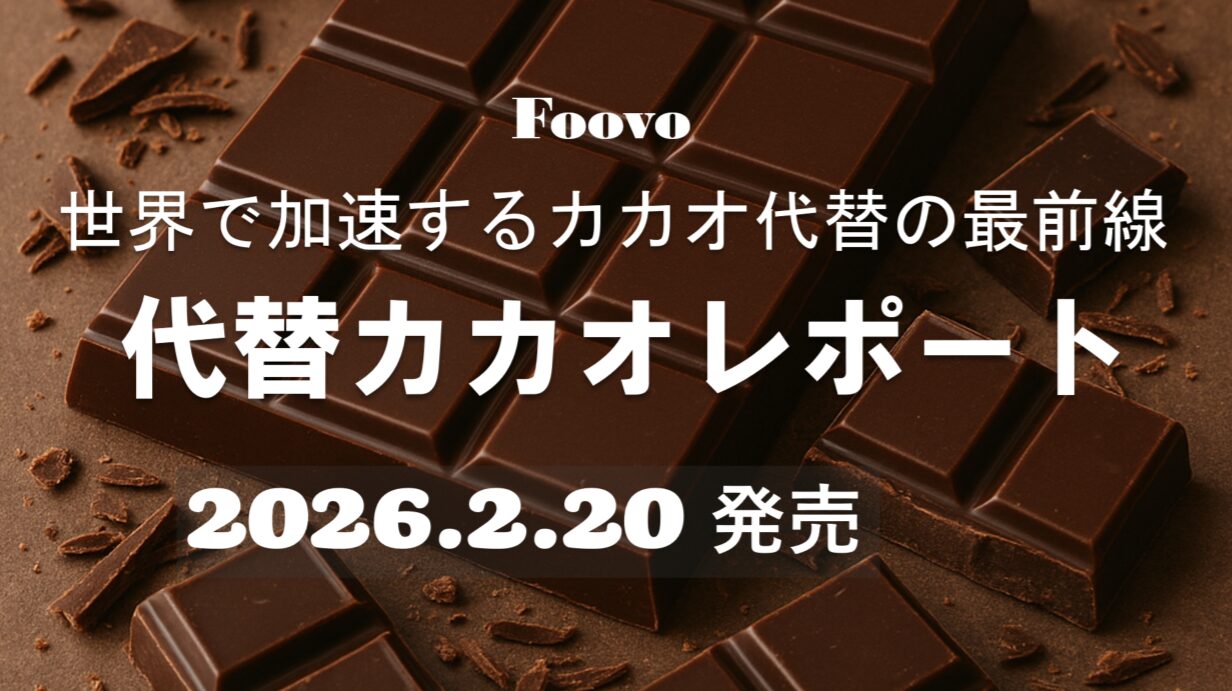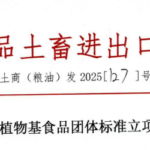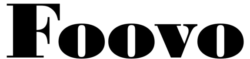牛に依存せずに、細胞培養ミルクを開発するOpalia(旧称Bettermilk)は2025年8月5日、世界大手の乳業サプライヤーHoogwegtと戦略的商業契約を締結したと発表した。
1965年にオランダで創業し、現在6大陸130ヵ国以上で事業を展開するHoogwegtは、Opaliaと2年間にわたる提携を通じ、細胞培養ミルクの商業化を支援する。
注目したいのは、この契約が単なるパートナーシップではなく、Hoogwegtが購入注文を行っている点で、販売認可取得後の具体的な市場投入を見据えた契約であることだ。
OpaliaのCEO(最高経営責任者)であるJennifer Côté氏は、「世界初の細胞培養乳製品の開発を支援するHoogwegtの購入注文は、当社の先駆的技術に対する信頼と関心の証であり、この購入注文によって、世界初の細胞培養乳製品を商業化できると確信しています」とプレスリリースでコメントしている。
具体的な数量や価格は開示されていないものの、オフテイク契約に近い性質を持つ可能性があり、規制当局の販売認可を取得後には、Hoogwegtの販売ネットワークを通じた市場投入が想定される。
細胞培養ミルク:培養肉、精密発酵との違い

出典:Opalia
2020年設立のカナダ企業Opaliaは、細胞培養によるミルクを開発している。
この分野では、フランスのNümi、今年破産が報じられたBiomilqなどがあるが、OpaliaはドイツのSenara、米Brown Foodsと並び、牛に依存しない培養ミルクの開発に注力している。
同社は2022年の時点で、製造プロセスからウシ胎児血清(FBS)の排除に成功していた。同年、乳腺細胞から4種のカゼイン、2種のホエイ、牛乳に含まれる乳脂肪と糖分を生産し、複雑性の実証にも成功した。
公式サイトによると、牛の乳腺から分離した細胞に糖、アミノ酸など栄養を与え、独自プロセスを使用したバイオリアクターで培養し、細胞から分泌されたミルクを回収する。
一般に、ホエイやカゼインなどの細胞培養ミルクは、乳腺上皮細胞で合成され分泌される(Kwon H.C. et al., 2024, J. Anim. Sci. Biotechnol., 15:81.)。つまり、培養ミルクの生成において、細胞は成分を合成・分泌する「ミニ工場」であり、最終産物にならない点で培養肉と異なる。
「ミニ工場」という点では精密発酵に似ているものの、精密発酵では特定の成分のみを生産するが、細胞培養ではミルクのすべての成分を同時に生産できる点が特徴となる。この点で、味や風味の再現性において有利に働くと考えられる。
一方、培養ミルクの規制環境は依然として未整備だ。細胞培養食品ではこれまでに鶏肉、牛肉、豚脂肪、サーモンなどが安全性を確認され、シンガポールやアメリカ、オーストラリア、香港で販売事例があるほか、最近では培養ペットフードがイギリス、シンガポールで認可されている。しかし、培養ミルクはまだいかなる国でも認可されていない。
価格障壁をどう乗り越えるか

出典:Opalia
培養母乳は粉ミルクなど特殊用途として高価格帯での市場投入が前提となるが、マスマーケット向けの培養ミルクで量産体制を構築し、価格競争力を備えるには、技術面・コスト面で依然として課題が残ると思われる。
こうしたなか、Opaliaが初期からマスマーケット向けの乳製品に挑む戦略、それを大手乳業サプライヤーのHoogwegtが初期から支持していることは注目に値する。
Hoogwegtは2024年4月の200万カナダドル(約2億1,000万円)の資金調達ラウンドでもOpaliaに出資しており、当時も「私たちは、Opaliaの牛に依存しない牛乳が、将来の持続可能な乳製品サプライチェーンの重要な構成要素になると確信しています」と、培養ミルクの可能性を高く評価していた。
なお、1Lの牛乳を生産するには628Lの水が必要とされ、牛の飼育は広大な土地使用、大量の飼料、温室効果ガスの排出を伴う。昨今は気候変動による酷暑で飼育中の牛の死亡例も報告されており、世界人口の増加に伴う乳製品需要に対し、持続可能な供給体制の構築は喫緊の課題となっている。
今後、Opaliaが商業化に向けてどのように価格障壁を乗り越えていくのか、Hoogwegtとの連携を通じた展開が注目される。
※本記事は、プレスリリースをもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。
関連記事
アイキャッチ画像の出典:Opalia